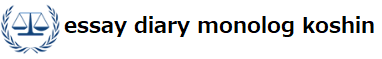いのちの初夜(北條民雄1936)について、コロナ禍での仕事の変調について
私の研修講師の仕事は、年末年始や、年度末年度初めは、所謂「仕込み」の時期なので、毎週のように地方出張することもなく、他の2つの仕事、相続等の民事の仕事や著作権・知的財産権の仕事をして、京都周辺にいることが本来は多いのである。
しかしながら、2020年春の、コロナ禍が始まってからは随分と変則的になってしまった。
2020年は、1年を通じてすべての仕事が激減して、貯金をつぎ込んで何とか凌いだ。コロナの特別給付金等は一時凌ぎで、本業そのものが仕事がないので、焼け石に水程度でしかない。取引先の助けの手も限られていた。
それは、現在も勿論続いているが、自分の社会的地位が思い知らされた。格差社会で、もうかなりこの国は固定している。
現在の日本は、かってのような「努力すれば報われる」のは、エリートの勝言葉に過ぎない。勝利宣言に過ぎない。高い地位に上っているものはそのままの人生があって、そうでないものはそこで喘いでうちに一生が終わる。
京都の町で、その「仕込み」時期と「講演受任」時期が交錯するようになってしまって、すっかり変調の日々を比叡山の峰を仰ぎ見ながら過ごす毎日になってしまっている。
仕事のリズムが完全崩れてしまっている。こんな時期にこれまでにないような仕事が詰め込まれている。どうやってリフレッシュすればいいのだ。知識の習得や考えをまとめる時間が極端に少なくなっている。好きな漱石・鴎外の著作もダメ。
例によって、短時間ではあるが、河原町六角の丸善書店、立命館大学の旧広小路校舎の散策から朱雀の大学院図書館での書籍探索がほぼ唯一の気晴らしである。
そんな時に、偶然 いのちの初夜(北條民雄1936)を手に取った。
いのちの初夜で、繰り返し出てくる「死との対話」、それは、人生に絶望をもって立ち向かう人間の心の奥底から出てくる言葉だ。それは、魂の再生だ。
私の人生経験の中で、何度か体験した私の「死との対話」のリアリティは、作中のリアリティと同じだ。
「命の再生」に最後至っているのは、私が今生きている理由そのものだ。
この作品は、圧倒的な力で私の精神を揺さぶった。
私が今一番危惧しているのは、いま私の人生に発生している「絶望」から、「死の対話」を自己の精神とした後に、再びこの作品の最後の行にあるような「命の再生」に至る事が出来るのか、それとも、作者が未遂に何度も終わったことをやり遂げてしまうのか、である。